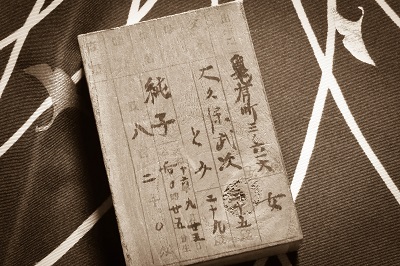怠惰な散歩 TOP 怠惰な散歩 TOP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卯月の風 わたしが住んでいる母屋の周り廊下のガラス戸を開けると卯月の風と匂いがさあーっと入る。「四月の風」とは認めたくない「卯月の風」だ。ライラックの白い花も咲きだしわたしの庭は春の海だ。 築山に目をやるとシャクナゲが淡いピンク色した大ぶりの花を広げている。そして目線を下げていくとオタマジャクシの卵がびっしり産まれた池の隅にゼンマイが土から顔をだし幼葉を渦巻き状に巻いた状態で伸びている。幼葉は綿状になりフワフワとしておぼつかない赤ちゃんのハイハイに似ている。ゼンマイには男ゼンマイと女ゼンマイがあるというから、さながら家族が共に力を出し合って成長していこうという姿に見え力がわいてくる。このゼンマイは同じような群れをなして庭のあちらこちらに咲いている。母が元気だったころは茹でたゼンマイを食べたが今はわたしが春を楽しむ鑑賞用となっている。 わたしは父が残してくれた大きな庭で四季折々の草花を愛でられることに深く感謝をし手を合わせる。父と母と弟たちと住んで幾多の歳月を重ねたのかー。そして、あたりに漂う家族の匂いを確かめるように卯月の爽やかな風に浸る。母屋の庭や裏山には、蕗のとう、ゼンマイ、山ウド、コゴミ、タケノコ、菜の花、タラの芽などが一斉に春を知らせる。その中でも春を一番先に肌で感じるのは福寿草が咲き始めたころ。もっと早く春を告げる足音を知らせるのは小枝にもっこり新芽が盛り上がりはじめたころ。思春期の子どものニキビのようなふくらみをじっーと目をこらして見ているともう冬も終りさぁー春だという歓びで全身に力がみなぎってくる。 母は精進揚げが好きだった。わたしは油の匂いでまいり天ぷらを揚げることは今でも出来ない。母はわたしが出かけ家を留守にした時に台所の窓はもちろん家中の部屋の窓を開けて天ぷらを揚げていた。家に帰ると微かに菜種油の匂いが漂ってくる。「今日のおかずは天ぷらだ」と分かってしまう。その微かないやな匂いを嫌うでもなく母が作ってくれた天ぷら料理をおいしく食べた。春の匂いを感じなら。食卓に盛られた色とりどりの旬の野菜を食べる。 摘み取ったばかりの菜花のおひたしもお膳に盛られる。でも、わたしは菜の花の蕾を摘み取ることはできない。なぜかというとさあこれから黄色い花を咲かせようとしている蕾を摘み取ってしまうことはとてもかわいそう。お花好きのわたしにとってそれは背信行為になるようで手が伸びない。わたしはいつまでも蕾から花開くまでを楽しんでいる。だが、母が作ってくれた菜の花のおひたしは平気で食べることができる。勝手といえば勝手で我がままかも知れない。それでも、卯月の風は爽やかに吹いてくる。今日は、いつもより青空が眩しく見える。 2018年4月6日 №02 |
  |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||